あの人がいないと業務が止まる…そんな不安はありませんか?
「これ、◯◯さんにしかできないから…」 「引き継ぎが大変で、新しい人に任せられない」
中小企業や少人数の現場でよく耳にする声です。 でも、そのままにしておくと──
- 教育のたびに毎回ゼロスタート
- スタッフの退職=業務停止
- 社長が最終確認しないと回らない
そんな”止まりやすい組織”になってしまいます。
そこで今回は、右腕サンが実践している「業務の仕組み化・マニュアル整備」について、実例を交えながら解説していきます。
1. 属人化とは何か?なぜ問題なのか?
■ 属人化とは:
ある業務を特定の人しか把握しておらず、その人がいなければ進まない状態。
■ 属人化の問題点:
- 引き継ぎ・育成コストが高くつく
- 担当者のミス・離脱でリスクが拡大
- 業務改善がしづらく、非効率が続く
社長自身が「自分しかできない」と思っている業務も、実は属人化のひとつ。 これは組織が“成長できない構造”を抱えていることを意味します。
2. 仕組み化とは何をすることか?
「仕組み化=すべてをマニュアルにする」ではありません。
右腕サンでは、以下のように段階的に進めています:
ステップ① 業務の棚卸し
- 誰が何をやっているか?
- どの業務が属人化しているか?
- 優先順位が高い業務はどれか?
ステップ② 業務フローの整理
- 手順の分解(例:請求書発行→確認→送付)
- 関係者・使っているツールの可視化
ステップ③ 手順書・マニュアル作成
- キャプション付き手順書(Googleスプレッドシート/Notionなど)
- 動画で残す場合もあり
- 「なぜこの作業が必要か」まで記載
ステップ④ 保守・運用ルールの設定
- マニュアルの更新ルール
- 新人教育への転用方法
3. 実例紹介:「経理業務の巻き取りと仕組み化」で業務が回り出したケース
ある経営者の方から、こんなご相談をいただきました:
「一人で抱えていた経理業務をお願いしたい。でも、どこから伝えていいのかわからない」
右腕サンでは、以下のようなサポートを実施しました:
- 経理業務のヒアリングとフロー整理
- 業務マニュアルの作成(手順書+ツールの使い方)
- タスクの分解とチーム内への役割分担設計
さらに、ロゴやLP制作など外注業務のディレクションも代行
結果として:
- 経理業務が仕組み化され、日常的な確認業務から解放
- 制作業務も進行体制が整い、事業の“土台”が強化
- 社長が動かなくても業務が進む状態ができ、他業務に集中できるようになった
「自分が動かなくても回る体制ができて、事業に集中できるようになりました」
4. マニュアルがあると“任せる”が変わる
マニュアルや業務設計があると、
- 社長やベテラン社員が「説明しなくても任せられる」
- 社内に“教え合える文化”が生まれる
- 新しい外注・アルバイトにも柔軟に対応可能
さらに、
- 「この業務、もっと簡略化できないか?」
- 「このフロー、無駄があるな」 といった改善の発見にもつながります。
マニュアル=”一度つくったら終わり”ではなく、 “成長する会社の土台”になります。
5. ベネフィットまとめ:仕組み化によって得られる変化
| 項目 | Before(導入前) | After(導入後) |
|---|---|---|
| 引き継ぎ | 都度口頭/時間がかかる | 資料+手順で即対応可能 |
| 業務の再現性 | 人によって精度がバラバラ | 誰でも同じ基準で対応可能 |
| 育成工数 | ベテランがマンツーマンで指導 | 教材をもとに“自学自習”が可能 |
| 社長の関与 | 細かい確認が必須 | 任せてOKな状態がつくれる |
まとめ:小さな会社こそ、仕組みで回す
「ウチは人が少ないから」「まだそこまでじゃないから」 と後回しにされがちな業務の仕組み化。
でも実は、少人数の今だからこそ“型”を整えておくことが重要です。
右腕サンでは、現場を止めずに仕組み化を進めるサポートをしています。
属人化を脱し、任せられる組織へ。
それは、社長が“現場から一歩引く”ための第一歩です。


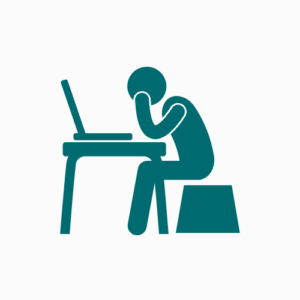
コメント